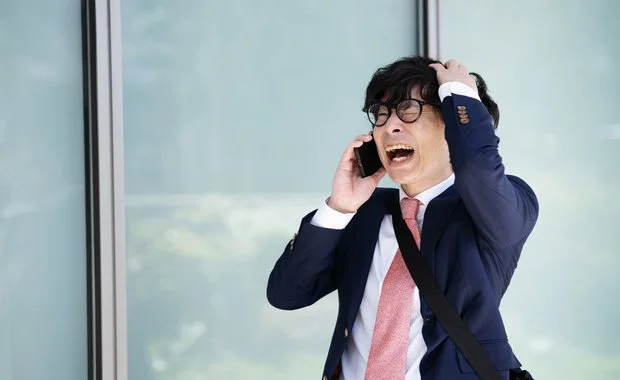- 2025.10.17
ベトナム人スタッフの問題意識と夢への姿勢を考える
多くの日本人管理者が、ベトナム人スタッフに対して問題意識が薄いと感じることが多いのは理解できます。問題意識が低いということは、現状に満足しているか、現状に適応できているため、改善の必要性を感じていないということになります。そのため、仕事においては受け身であり、改善提案や改善活動への意識が生まれにくいのです。ボトムアップ的な経営を目指す理系企業の経営管理者にとって、この姿勢が不思議であり、不満や不可解さを感じるのも無理はありません。 問題は大きく三つに分けられます。まず顕在的な問題は、緊急性が高く誰にでも明らかな課題で、例えば明日の生活費をどうするかといったことです。次に潜在的な問題は、現在の生活には問題がないように見えても、背景にあるリスクが表面化した際にどのような影響があるかを考える必要がある問題です。最後に、自己実現的な問題として、現状に満足してリスク対策を講じているものの、より高次元の目標や夢を達成するために克服しなければならない課題が存在します。 現状に満足し、改善の必要がないと感じることは、精神面では良いことだと個人的に思います。満足しやすく、日常を楽しみやすいことで、最終的には幸福感を得やすくなるからです。しかし「無知の幸せ」という考え方もあります。これは、事故や病気、子育てなどの人生における様々なリスクについてあまり意識せずにいることから生まれる幸福感を指します。つまり、起こり得るリスクを知らない、あるいは無視しているために、今の状況に安心しているのかもしれません。そうではなく、リスクを理解していること自体が問題を認識する第一歩だと言えるでしょう。 日本では四季があり、特に冬には準備や蓄えが不足すると命に関わるリスクが常に存在します。また、自然災害も頻繁に起こるため、日常的にリスクと向き合いながら損害を減らしリスクをヘッジする習慣が身についています。そのため、比較的気候が安定しているベトナムよりも問題意識が高いと考えられます。一方、ベトナムでは社会の発展とともに平均年齢が30代前半となり、親世代の医療費や中年世代の子育てコストなどがより意識されるようになってきています。社会の発展に伴い、物価の上昇とともに問題意識も高まっていくでしょう。 裕福な家庭や一定の地位と収入がある中間管理職に関しては、生活リスクから解放されているため、夢を尋ねると多くの人が早期退職を挙げます。早期退職後の希望は、遊ぶことやゆっくりすること、農業や世界一周旅行など、楽しみに関するものが多いです。それを見ると、今の仕事はそれほど苦労が多いのか、楽しめないのかと疑問に感じます。また、多くの人にとって仕事は自己実現の手段ではなく、稼いだお金で好きなことをするための手段になっているように見えます。しかし、遊びもすぐに飽きが来るものであり、それだけで満たされるわけではないと私は思っています。それでも、早期退職は一つの大きな夢として広く認識されています。 日本のメディアでは「日本一」や「日本初」といった言葉がよく使われ、プロジェクトXのようにチームで達成する夢が称賛されがちです。一方、ベトナムでは「ベトナム一」という言葉も使われますが、普通のものを努力して作り上げた結果に関することが多く、例えば大きなラーメンや仏像といった、人々の夢とは直接関係のないものが中心です。 また、日本では仕事の話が職場外の集まりでも行われることが一般的ですが、ベトナムではオフ会はリラックスするための場であり、仕事の話をするのはタブーとされています。仕事の話を持ち込む人は、雰囲気を壊しがちで、周りから敬遠されることが多いです。こうした状況から、個人レベルで夢を語り合い、高次元の目標を共有して応援し合う文化はベトナムではまだ希薄だと感じます。 とはいえ、ベトナムのような開発途上国では、大きな夢を持つことは一般的に難しいとされています。社会や政治的にも「出る杭は打たれる」風習が根強く残っており、大きな夢を持つことは無謀だと見られがちです。しかし、約30年前に日本に留学した際、日本の若者が音楽バンドやストリートアートに情熱を注ぎ、夢を追いかける姿にとても憧れを感じました。そのような人々が自分の夢を追いかけることで、周囲に与える影響は非常に大きいと実感しました。 現在のベトナムでも、バンドや伝統芸能、コメディアングループなどが増えつつあり、夢を追いかけながら生計を立てることが可能な状況になりつつあると感じています。生活がだんだんと安定してくることで、ベトナム人も夢を本気で追うことができるようになるでしょう。若い世代やサラリーマン世代でも、会社の中で夢を語る機会が増えてくるのではないかと思います。 もちろん、若い世代に期待するだけでなく、今の中間管理職も自ら行動し、仕事の中で自分の夢を見つけることが大いにプラスになるはずです。どのようにすれば夢を持って挑戦する意識を育てられるかについては、今後さらに考察したいですが、夢を持つことの重要性を改めて強く感じています。
- 2025.07.14
ベトナム人の計画性のなさ
ベトナムとご縁があって、ベトナム人の結婚式に呼ばれて、出席したことがありますか? 招待状には午後6時からスタートと書かれているため、まじめな日本人は6時前から来ますが、開宴時間はほとんどは7時過ぎ、雨なんかでひどい時は7時半まで待たないといけない。悪いことに、どうせみんな遅れるから早く行くと損すると思って、この慣習は一向に変わる気配がありません。早く来るマジメな人たちは損する形になってしまっています。 もう一つ記憶に残る事例がありました。 ベトナムで少し前まではヘルメットを着用するのが義務化していませんでした。 それが、義務化になったのは2007年12月15日でした。そのために、法律施行するずっと前に(どうもそれがJICAの支援らしいですが)バス停やビルボードなどで、ヘルメット着用を促す大規模な告知が行われました。そこで、何か起きたかというと12月14日の夕方以降ヘルメット売店には購入者で長い行列ができました。ヘルメットを購入して翌日の法律施行に間に合わせるためでした。全国民が一気にヘルメット着用義務化されるということで、法律施行できないではないかという心配を一掃する国民の順応性で、世論を驚かせましたが、直前にならないとアクションをとらない性質が浮き彫りになる現象でした。 弊社のベトナム人社員を見てみても、こういう直前なアクションが多々あります。突然な休み申請はとても多いですし、提出物はほとんど期限ぎりぎりです。そこで、計画性欠如の原因を分析してみました。 ⭐ 其の1:そもそも計画することすら嫌っている(教わっていないとも言えます) ソーシャルメディアでよく拡散される内容の中で、「値段を気にしないで買い物できるぐらいのお金を持ちたい」、「お金を気にせず旅行したい」のような考えがかなり支持されています。かなり高い金銭志向を持っています。そもそも大金持ちはごく一部でほとんど国民は金銭的に工夫することで、限られたお金の中で最大限楽しむノウハウを学習する必要があります。一般的に、「楽しいことをしたい➡計画/工夫する➡お金を含めて、いろいろ準備する」のようなプロセスが考えられますが、大金持ちではないので、計画もしたくない、楽しむのを諦める、とまさに逆の思考プロセスが起きています。 ⭐其の2:安い労働力に支えられる無計画性(便利さ) 上記の結婚式の話にも通じますが、遅れても損しないため、早く行く損を被るよりかは遅く来ようとなってしまっています。優しい国民性だからかもしれませんが、その背後には安い労働力に支えられるからと私はみています。安い労働力があるから、宴会が1時間長くなってもレストランにとって、大きなコストアップになってないため、うるさいこと言わず、サービスしちゃうと。家に書類を忘れたら、安い運賃でGrab Deliveryですぐ届けてくれる。腹減ったら、そこらじゅうの地べたのラーメン屋で一服できる。思い立って、遠出したかったら、運転付きの車を借りて、すぐ出かけられる。これらすべては安い労働力に支えられる無計画性(でもかなり便利)だが、経済発展につれて、労働賃金が高騰すると、状況も変わって行きます。 コスト高になり、学生を採用しづらくなる➡計画的な定期採用になる 車を保有するコスト高くなり➡公共交通にシフトしていくと、運転ダイヤルに合わせないといけない 個人事業主としては稼げなくなり➡サラリーマンになる➡規律のある計画的な生活に順応する 生活維持費が高くなり、キャリ重視する(コラム19を参考に)➡計画的な思考になる ⭐其の3:計画的な人ほど損しやすい社会情勢 数年前にハイフォンからハノイへ路線バスで移動したことがあります。正規なチケットで乗車したわけだから、正規な席が約束されるはずだが、運転手が個人的に現金を受け取って、無理やり席数以上の人数を押し込んでいました。おかげで、席の一部を譲らないといけない非常に不快な旅でした。これは運転手がバスを所有している権利を乱用した事例ですが、VIPの知り合いだから優先されるなど、利権を乱用され、正しい行いをする人たちの権利を損なっている形になってしまいます。逆に計画を守ろうと思うと今度、戦わないといけず、エネルギー消耗されます笑。 社会が発展していくと上記の仮説②および仮説③が自然によくなるとみています。 一方で、仮説①である個人的レベルの楽しみ方や計画性は学校(部活)や家庭内でしか教わっていないため、法人として、この楽しむ➡計画性プロセスを応援するような活動があると最高によいと思っています。社員および会社でお金を積み立てて、慈善活動に回す、社員旅行予算を業績連動させる、などなどが考えられます。弊社も実施に向けて、組合長と相談してみることにします。
- 2025.06.14
こだわりのないベトナム人
私が日本留学している1998年頃に、たまたまベトナム中部で大きな台風と洪水に遭い、大変な状態になっていました。ベトナム全国から募金活動が行われ、日本にいた私もベトナムのため何かに貢献したいと思い、当時私が入ったロータリーアクトクラブメンバーに相談してみました。自分の地域で募金しようということになり、さっそく作戦会議が行われました。随分時間も経っているので、詳細は覚えていませんが、延々と続いている作戦会議、誰も帰ろうとしなかったことはよく覚えています。その後、募金箱を作って、その地域のほぼすべてのお店に募金箱を置かせてもらって、最終的に50万円も集められ、私がそれをベトナム領事館を通じて、ベトナムに送金することができました。 ※今なら、セルフィ写真を撮って、Facebookにアップしたいところですね笑。 今思えば、当時の長い長い会議というのは何とかベストな成果を出したいという強いこだわりがあるから、そうなっていると分かります。その後、日本で、就職して、「手に誇れる商品を作れ」というようにこだわりを持って、仕事に取り組むことを教わったわけです。時には拘り過ぎてしまうこともある気がしますが、日本という社会そのものはこだわりの塊という見方もありかと思います。 それに対して、弊社のスタッフをはじめとして、一般的なベトナム人はこだわっていないじゃないかと思わせることは多々あります。ミススペルだらけの文書でも、平気で提出する。体裁が整っていない資料を作ったり、質の低いレポートで済ませるなどなどです。そもそも、指摘しても、同じミスを平気に繰り返しているのは自分を高めていくことに対してこだわっていないかもしれません。 実はベトナム語ではこだわりと相応する言葉はありません。言葉がなけれ、概念も生まれないだろうと思います。近い意味として、Ngầu (ガオ)は英語のCool、日本語として、カッコイイぐらいです。つまり、拘ろうではなく、カッコイイことをやろうという言い方になります。そういう意味で、拘りは自分に対しての基準であり、カッコイイは他人の基準に依存するものです。日本人は自分の基準で貫くが、ベトナム人は評価される方でカッコイイ自分でありたいように思います。日本人は部下のよくない点を指摘して、育てるのに対して、ベトナムスタッフは良い点をほめて育てる方が自然でしょうね。 その一例として、弊社ではでは各部署で持ち回り制で月末に懇親パーティーを開催する恒例行事があります。これまで1年近く回してみました。まったく狙っていなかったが、面白いことにだんだんとこだわりが生じてきています。どうも、他部署よりよくしようという思いが生まれているらしく、出す料理、パフォーマンスが創意工夫され、パーティーの楽しさや充実感が回を重ねて、増しています。この一例で大いに学ばせてもらいました。 ① 仕事もパーティーのように楽しくすること ② どんな作業もなるべくシンプルに反復させる ③ 反復していく中で、前回の良かった点を踏襲し、今回にプラスアルファを実施し、全体を楽しむ 別の観点でみると、上記はPDCAサイクルそのものであり、新しい発見でもなんでもありません。しかし、強調したいのは仕事も楽しくする工夫と、スタッフのプラスアルファをしっかりと応援する。成果が上がれば、しっかりとほめることです。そのうちに、スタッフも成長して、カッコイイ自分に惚れ、プラススパイラルにハマり、自立します。
- 2025.05.13
スタッフの主体性が低いのは日本人上司の責任!
弊社は長年日系企業向けの人材紹介をビジネスとしているため、何か非日系に対して、できないかを考えたときに、日系企業で経験を積んだ人材を非日系企業へ紹介しようと考えた。責任感高く、ホウレンソウができ、技術も抜群によいため、引手余るではないかとみた。しかし、予想を反して非日系では日系人材に対して、さほど興味を持ってくれなかった。理由を尋ねると、「日系人材はYESマンばかりでリーダーシップがないから」と言われた。悲しかったが、そうみられたんだなと改めて認識した。 一方で、日本人管理者から見ても日系人材は満足するようなリーダーシップを発揮しているわけではないそうだ。確かに日系企業において、現地人のリーダーは少ないようにみえる。そもそも、リーダー格人材がいないのか、育てられていないのか、リーダーシップを殺してしまっているのか意見が分かれるところではあるものの、日系企業ではなかなかリーダーが出てこないのは事実である。 何か原因か考えるときに、下記の3点を挙げることができる。 日本人上司によくある過ちは相手ができていない前提で見ている。スタッフができないだろうと考えて、手取り足取りして教える。一見やさしいように見えるが、場合によって、相手の自主的な考えを殺してしまうことになる。教えられる側は以降、自主的な考えを辞めて、日本人上司の助けを期待する。日本人上司側はスタッフはやはりできないと確信して、文句を言いながら、喜んで、助け続けている。 採用支援させて頂いている会社では「現在いる社員で頑張っているこの中から幹部にする」というのをよく耳にする。私が知っている限りではこの方式でうまく行く例はほとんどない。そうみているうちに、有望なスタッフが転職してしまうか、望むような成長がどうやっても得られないので、いつ経っても幹部に相応しい人材が出てこない。一方で、明確に本人に幹部として、育てると示せば、転職せずに頑張るし、管理者になるための知識、スキルを身に着け、数年でもあれば、立派な管理者になる事例はたくさんある。社員の成長を待つのではなく、ポテンシャルを信じて、期待を込めて、アサイメントすることだと思う。 人事評価フレームワークのない多くの日系企業は平均主義な評価をしている傾向がある。営業部隊の評価を例にして、いうと、売り上げ目標に対するコミッションがない上、ボーナスの差もあまりない。長期的にコミットする文化のないベトナムでは短期的な見返り(報酬)を求める。それだと、頑張っているスタッフは不公平と感じるので、やる気をなくして、最終的に転職してしまう。公平に評価して、できる人をしっかりと伸ばし、できない人を辞めてもらうことが活性力のある組織作りの条件ではないだろうか。 そもそも、ベトナム現法のボスである駐在員はしっかりとした管理者かというと大いに疑問。管理経験がない、本社より権限が与えられない駐在員も多い中、ベトナムスタッフに主体性やリーダーシップを求めるのはやや理不尽な気がする。 まず、駐在員自身が会社の中で、期待される存在になり、ベトナム現法のパフォーマンスが正しく評価されるようにするのが先決だと思う。そのうえ、ベトナム人スタッフに期待して、その期待を明確に示して、そして、成果を正しく評価する。そうすれば、組織も活性化し、主体的に動くスタッフが増えるはずである。
- 2025.04.11
言い訳が多い病
ベトナム人のスタッフは言い訳が多いことは当たり前のように言われ続けています(汗)。 何か問題が起きた時に、その報告を求めると、延々と理由から始まり、理由で終わっています。 結果は何なのか?本当の理由は何か?今後に繋がる反省ポイントや対策などはまったくと言っていいぐらい、言及されないことの方が圧倒的に多い。 弊社スタッフでみると、いろいろと報告のやり方などを教えると半年~1年ぐらいでやっと報告らしい報告になります。それにしても、深いレベルでの原因究明や対策はまだまだです。代表的な事例をまとめてみました。 指導ポイント ケース 期待される効果 報告は結論を先に行ってください。 延々と理由から入るので、すぐ止めて、「報告する方法を教えましたね。それに従って、もう一回報告してください。」と指示 スタッフはビックリして、結果を報告するようになりますが、この指示を10回でもしないと、習慣化されません。 選択肢をあらかじめ用意して、上司に伺い立てる 結論で終わっているケースもあれば、結論の後に延々と理由が続いているケースもある。「どうしたいの?」、「私(上司)に考えさせて、自分の意見はないの?」、「私(上司)が君のアシスタントではない」、「私に仕事を増やすな、自分で考えてこい」のような言い方をして、考えることを促す。 現状を報告したら、上司が考えて、対処方を教えてくれると勘違いするベトナム人スタッフが圧倒的に多い。このように突っ込まれて、初めて頭を使う子も少なくないはずです。何回も何回もこの会話をしないと、考えてくれません。 期待をはっきり伝えること ある課題に対して、延々と現状報告をして終わる。報告する上司に何を期待して、何をやってほしいかよくわからないことも多い。「何をやってほしいの?」と回答させる。 上記同様、上司が考えてくれると期待したので、はっきりと上司に対しての期待をすぐ応えられない子もいます。これを繰り返すと、そのうちに自然とチームワークができて、相談もできるようになります。 問題があれば、すぐ報告してください。 自分で処理できるとは思っていませんでしたと思うスタッフも少なくありません。とくに問題と認知しないことはとても育成しづらい。鈍感と言えるかもしれません。場数を増やして、失敗から学ぶしかないと思っています。 上記のOJTを6か月~1年でようかくまともな報告ができるようになりますが、なぜ、社会人の若年層ではこのような傾向が強いのかについて、考えたり、議論したしたことがしばしばあります。深い話ですが、何個か事実を見えてきました。 ・教育方法:ベトナムの学校では何か問題を作った学生には反省文を書かせます。やってしまった悪さは同じでも問題を引き起こした背景や理由を考慮する習慣があります。その教育を小さい頃から受けると逃げ道として、たくさん理由を探す習慣が形成されてしまいます。ビジネス業界でいくら理由があろうと考慮してもらえない、許してもらえない事実を伝えることを繰り返し、個人に理解分からせてあげるとだんだんと理由探しの癖が剥がれていきます。 ・無宗教:そもそも、言い訳する目的は責任を取りたくないあるいは責任を軽減したいからである。責任をとると自尊心(プライド)が傷つき、みじめになる自分を許せない。あるいは単純に怒られるのが怖い。宗教観を持ていれば、自分よりもずっと偉大なる神がいて、誠実な自分で生きていれば、神に近づけるという考え方を持っていれば、素直に自分の非を認めることになりますが、無宗教なベトナム人が多いので、実はあまり期待できません。 ・家庭環境:ベトナムの家庭では日本と比較して、子供の個性を許容しない傾向がある。意識してそうしているではなく、子供によくしたいがために、いろいろ強制した結果である。個性が許されない子供はどこか元気がなく、さらに自分の個性(プライド)が害されるではないかと心の中で、感じるはずです。そうやって、個性を保ちたい=ミスを認めたくない構図になる。言い換えると愛を十分に与えられない子供はなかなか勇気をもって、自分の非を認められないということになります。 ビジネスの場面ではどうにもできないことばかりかもしれませんが、背景を理解すれば、許しやすくなり、仕事もしやすくなりのではないでしょうか?私の会社ではまず、個別に指導することと個性豊かな会社には作りたいと思っています。それができれば、次第にスタッフにも波及することを願っています。
- 2025.03.10
ベトナム人スタッフはなぜ、相談しないのか?
弊社のスタッフに文書作成を依頼した際に、詳細な内容を教えた後、「できますか?」と尋ねたところ、「はい、できます。」と答えました。期日が来て、状況を確認したら、作成された文書は予定と異なる内容になっていました。その理由を尋ねたところ、「私はこのように理解したから、変更しました。」とのことでした。「なぜ、相談せずに、許可なく自己判断したのですか?」と聞くと、「この仕事は任せられたから、自分で判断できると思ったからです。」という答えがありました。 同じようような経験をされた方も多いのではないでしょうか。他にも多くのシチュエーションがあります。 仕事をお願いしたら、全く報告がない メールで外部とやりとりする際に、故意に上司へCCしない 報告がないので、今、何をやっているか周りは全くわからない 報告を求めたら、違うやり方でやっていることが発覚する なぜ違うやり方をしているか聞いたら、他のやり方のほうがよいと言う 等々。 相談することは個人の成長や問題解決に非常に有効です。問題や悩みが自分自身で解決できない時は、他の人からアドバイスを得ることができます。他の人には異なる視点や経験があり、自分にはないアプローチを教えてもらえることもあります。相談することで自分の考えや意見を明確化でき、意見に自信を持つこともできれば、他の人とのコミュニケーションを深めることもできます。少し勇気が必要ですが、上司に責任転嫁することもできるため、相談しないより相談する方が明らかに賢明です。しかし現実には、スタッフにこのことを教えても、頭では理解してくれてますが、実際はなかなか相談してくれないので困っています。 考察の結果、相談を避ける理由は以下のようになります。 ①問題が認識されていない 自分が知らないことを知らないということは幸せな場合があります。スタッフに問題があるか聞いたところ、ほとんどの人が「問題はない」と答えていますが、これは無知の幸せといいますか、問題を認知していないことを示しているかもしれません(それは相談しづらいという理由にもなりうる)。問題を認知しない理由にはいろいろありますが、目標が明確でない、あるいは目標設定が不十分なこともあります。その為、チームのパフォーマンスを数値で確認し、平均値以上のコミットメントを求めることがよいとされています。 ②問題が認識されていても、自分は解決する役割ではない、又は解決する必要がないと考えられている 例えば、日本人はゴミを見つけた時、自分が捨てた物でなくても片付けますが、ベトナム人は他人のことだと考えて放置します。これは学校、家庭、社会の仕組みも関係していて、国民性とも言えます。ベトナムの学校では勉強だけが重視され、日本で行われるような掃除、給食の手伝い、運動会、部活などはありません。親がバイクで学校まで送ってくれ、給食は栄養士のおばあさんが担当し、勉強が終わったら塾に向かいます。家庭では家事はお母さんの仕事で、子供たちは勉強だけに集中すればよいと考えている家庭も多いため、何もできないまま社会人になるということもあります。職場では他人に興味を持たない、後輩に関心を示さないという環境があります。この無関心さが原因で、他人の課題を積極的に解決することができないと私は思います。 ③いろいろな心理的な障壁の存在 相談することは、自分ができていないことを認め、他者のアドバイスを受け入れるプロセスです。これは、自分の殻を破り、他人を受け入れる勇気を必要とします。また、アドバイスに従う勇気も重要です。しかし、自分の弱点を指摘されることや迷惑をかけることを恐れるため、多くの人は相談を避けがちです。このような心理的な障壁を乗り越えると、自分と他者の世界が交わり、より良いチームワークが実現します。相談が少ない環境では、決して、良いチームワークは生まれません。 ④問題が認識されていて、解決するために相談したいが、なかなか相談するのが困難な状況である。 例えば、先に挙げた2点はスキルを磨く内部的なものである一方、相談しづらいという感覚は外部的と言えるかもしれません。人間は極めてアナログな生き物で、相談すべきと分かっていても相談しづらい雰囲気であれば、大半の人は相談を辞めてしまいます。私はビジネスオーナーであることもあり、優しい自分をいくら演じてもスタッフからは敬遠されがちです。そこで、例えば、子供と一緒に見たいテレビ番組について若者に人気のものをスタッフに聞いてみたり、若者に人気のスイーツ店やレストラン、ファッションの話題を取り入れることも一つの方法かもしれません。 スタッフに思考方法を教えるためには、まず現状と将来のビジョンのギャップを明確に理解させることが重要です。ベトナム社会では、気候的に生活しやすいため、将来を深く考えたり予測する習慣が根付いていないかもしれません。そのため、問題意識を高めるには、現状をしっかり認識し、将来のビジョンを具体的にイメージする力を養う必要があります。このイメージは、今すぐのことから近い未来、さらに遠い将来まで様々な時間軸に渡るもので、人生のイベントに関連づけながらスタッフと情報を共有し、理想の姿を描かせることが大切です。例えば、キャリアのこと、結婚、出産、子供の育成、子供の海外留学、老後など様々なことが考えられます。こうしたプロセスを繰り返すことで、スタッフの視野が広がり、問題を正確に捉える力がつき、結果として問題意識が高まるでしょう。 相談し合い助け合う文化を会社のDNAにするためには、日常的にお互いに興味を持ち、考えを共有することが重要です。例えば、社内の定例会議は内容が決まっているため、問題がなければ早く終わりがちで、マンネリ化することも多いでしょう。しかし、会議の後に少し時間をとり、スナックを食べながらコーラを飲んで、互いの困っていることを共有する時間を設けるのは良い取り組みです。最初は不自然でぎこちないかもしれませんが、続けることで次第にチームワークや一体感が生まれ、楽しめるようになるはずです。相談ができない状況は、個人の問題ではなく企業文化の問題だと考えられるため、それを解決するために全員が協力し、会議後の相談時間を有効活用することが大切です。この取り組みは、会社の文化を根本的に変えるプロジェクトであり、全員で自分の殻を破り、一体感を持つことが必要だと説明すれば、理解されるはずです(もちろん、上記の問題分析をしっかりと行っていることが条件です。それがなければ、単なるどうでもよい雑談で終わってしまいます)。